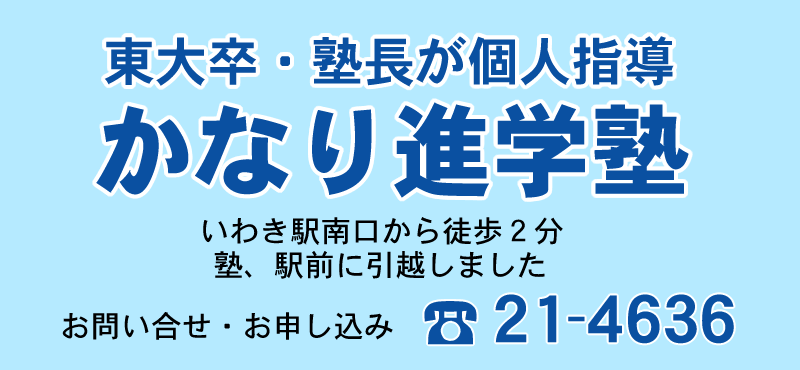 |
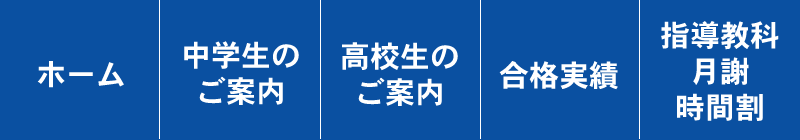 |
| 高校生ワンポイント |
| バックナンバー 2025.7月分 2025.6月分 2025.5月分 2025.4月分 |
| 7月 その1>> <高校生ワンポイント> 高3男子・母> 大学、見つかりました <質問> 息子の大学ですが、気に入った所が見つかりました。 前回、ある県の県立大にオープンキャンパスで出てみて。 でも、彼がイメージしていたのとは微妙にズレていて。 彼はバリバリの情報系が希望。 ですが、そこはメディアと情報を融合したような感じ。 いまひとつピンとこなかったようです。 そこで今回、別の県にある県立大のオープンキャンパスに出てみて。 そこが、まさに彼がやりたいことズバリ。 さらに環境も良くて。 広大なキャンパス。 設備も新しい。 とても気に入り、そこを第一志望に決めました。 ・・・ ただ入試ですが、バリバリの情報系だけあって数学重視。 共通テストでも数学の配点は高いし、2次試験は数学のみ。 1次と2次を合計すると、その半分以上が数学の点数。 もともと数学は好きで得意でしたが、さすがにこの配点には焦ったようです。 この先、数学の勉強はどのように進めたらよいですか。 <回答> お気に入りの大学、見つかってよかったですね。 やはり、これは大きい。 ご本人のヤル気がまったく違ってきますから。 とはいえ県立大。 国公立大ですから人気は高い。 入試レベルも高い。 そこをクリアしないといけません。 でもね、やるしかないですよね。 当たり前の結論ですが。 ・・・ 数学の勉強> これに全力を傾ける。 入試突破の条件はまさにそこです。 じゃあ、何をやるか? ズバリ黄チャートがおすすめ。 逆に、青チャートまでは不要。 これが国公立大の医学部を目指すというなら、青チャートしかない。 でも、情報系とはいえ県立大。 そこまで競争のレベルは高くない。 むしろ黄チャートを2周・3周して完璧にモノにしたほうが、合格の可能性は高くなります。 |
| 7月 その2>> <高校生ワンポイント> 高1女子A> 定期テストやばい <事例> AさんはB高。 迷った末、結局、吹奏楽部に入った。 「勉強が大変になるかも」という不安はあったが、部活の魅力には勝てなかった。 部活は思った通り楽しかった。 練習は大変だが、充実した毎日。 部員数が少ないこともあり、大会には小編成部門で出場することになっている。 もちろんAさんもそのメンバー。 さらに6月には定期演奏会もあった。 舞台に立ったAさんは、とても感激したそうだ。 素晴らしい会場。 「最高!」と思ったそうだ。 が・・不安は的中。 やはり勉強時間が足りない。 6月には前期の中間テストがあったが、まるで準備が追いつかなかった。 結果は無残。 これまでに取ったことのない点数。 どう巻き返せばよいのか、途方にくれている。 <分析> 試練が来ましたね。 でも、予想されたもの。 慌てず騒がず、淡々と対処していきましょう。 1 まず敗因分析 大事なのは、次の2つ。 ・なぜ勉強時間が取れなかったか 一番の原因は、部活です。 でねっ、それは今後も続く。 ならば、次回のテストで十分に勉強時間を確保するには、どうしたらよいか。今から対策を練っておく。 2 どの科目がやられたか 悪かったとはいえ、一律にやられたわけではないはず。 無惨にやられたのもあれば、比較的軽傷ですんだのもある。 それを見極める。 というのは、得意科目を作る必要があるから。 将来の大学入試を考えるとね。 それには軽傷ですんだ科目に注目する。 なぜなら、得意科目の候補だから。 ただただ途方にくれるだけじゃなくて。 冷静に現状分析しようね。 |
| 7月 その3>> <高校生ワンポイント> 高2女子B> 数学ついていけます <事例> Bさんの高校は進学校。 なので、数学のスピードは速い。 入学した年、年内には数学1Aを終えていた。 年が明けると数学2Bがスタート。 すでに数学2Bは半分近く終わっている。 Bさんは文系クラス。 なので、理系クラスよりはスピードが遅い。 理系クラスは、すでに数学2Bを半分以上終えているとのこと。 ・・・ さて、定期テスト。 6月には前期の中間テストがあった。 2Bはやはり1Aより難しい。 結果、Bさんは1年生の時より点数を落としてしまった。 「あんなに勉強していたのに・・ Bさんはちょっとガッカリ。 が、順位が返ってきてビックリ。 逆に順位は上がっていた。 内容が難しくなった分、平均点は下がっていたようだ。 Bさん、ヤル気を取り戻した。 この調子でがんばろうという気力も湧いてきた。 <分析> 良かったですね。 軌道に乗ってきたようで。 今回、2年生のBさんは好調。 それに比べ先ほどの1年生のAさんは・・ でもね、悲観することはないのです。 2年生は、1年生の未来の姿。 Aさんも、いずれきっとそうなりますから。 ・・・ さて、Bさん。 先生を志望することにしました。 そして文系でも、数学が好きだし得意。 ならば「中学校・数学の先生を目指しては」。 ちょっと文系の方には裏技のような私の提案。 受け入れてくれて嬉しいです。 数学2Bもついていけるようなので、この調子で勉強を続けてほしいですね。 そして、もし無理だったら別のタイプの先生を目指せばよいのです。 他の科目の先生とか、小学校の先生とか。 気になる点を2つ: 1 数学3 Bさんは文系。 なので、数学Cはやるかもしれませんが、数学3はやらないでしょう。 この科目をどうするか、ですね。 アイデアがあるので、いずれお伝えします。 2 国公立大 Bさんは私立大タイプ。 ですから、受験は3科目ですみます。 数学も2BまででOKという所が多いでしょう。 でも、国公立大を受験するとなると、数学3を要求されるはず。 その時、どうするか? こちらも、いずれお伝えしますね。 |
| 7月 その4>> <高校生ワンポイント> 高3男子C> 英検2級にパスした <事例> Cくん、私のすすめにしたがってバリバリと英語を勉強し始めた。 苦手な数学は、いったん置いておくことにした。 もともとコツコツやるのは好きなタイプ。 そのスタイルが得意でもある。 そこに情熱が加わったから、まさに鬼に金棒。 集中して勉強を進めている。 6月に英検のテストがあった。 Cくんは試しに2級に挑戦。 見事、筆記に合格。 「面接は自信ないです」と言いながら、塾の教材を何度もくり返し。 「耳には自信がなくて・・」 弱点を克服すべく、何度もCDを聞き返し。 結果、面接もパス。 Cくん、喜色満面でした。 「英語って、勉強すれば伸びるんですね」 何かをつかんだよう。 その自信は大きい。 ・・・ まずは英語で一点突破を目指す。 学年上位に食い込むべく。 そして国立大・合格の目安である学年50番という壁を破れるかどうか。 定期テストでも模試でも。 その壁にチャレンジ。 <分析> まずは第一段階クリア。 そんな感じです。 彼を見ていると 「目標が明確になった時、人は成長するんだな」 と感じます。 高校の先生はよく「早く志望校を決めるように」と生徒さんを促します。 時には焦らせるくらいに。 それは、こういう効果を狙ったものなのでしょう。 経験上、そのことを高校の先生は熟知している。 高3の受験生ですから。 年が明けると、すぐに共通テスト。 残り6ヵ月。 ぐずぐずしている暇はないです。 ・・・ これからの作戦: ズバリ英語の一点突破。 国立大は5教科7科目ありますが、中心になるのは数学と英語。 そのどちらかを引き上げる。 合格点よりずっと上まで。 そして、他の科目はそれに引っ張り上げてもらう。 Cくんの場合、それは英語。 このまま英語の勉強を続ける。 心中するくらいの覚悟で。 すると道は開けるはず。 |
| Copyright (C) 2004-24 Kanari-Shingakujyuku. All Rights Reserved. |